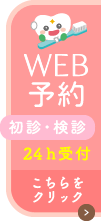指しゃぶりは、安心感を得るためのお子様なりの行動であり、必ずしも悪いものではありません。
しかし「指しゃぶりを続けているけど大丈夫?」や「猫背が気になるけど、歯並びに影響するの?」 など、子供の歯並びや姿勢に悩むパパママが多いのではないでしょうか。
そこで今回は、歯並びに悪影響を与える習慣や、今すぐできる改善方法について解説します。
歯並びに影響する姿勢のクセとは?

子どもの体は成長段階にあり、わずかな力のかかり方で発育の方向が決まります。そのため、日常の姿勢があごの発達や歯並びに大きく影響します。
特に次のようなクセがある場合は注意が必要です。
– 椅子に座るときに片側に体重をかける
体のバランスが崩れ、あごの発達に左右差が生じやすくなります。
– 同じ方向を向いて寝る
片方のあごばかり成長し、噛み合わせがズレる可能性があります。
– テレビを見るときに姿勢が崩れている
長時間悪い姿勢が続くと、歯並びにも影響が出やすくなります。
– ほおづえをつく
片側のあごに圧力がかかり、歯の位置がズレる原因になります。
– 猫背や首が前に出ている
下あごが後ろに引っ込みやすく、口呼吸につながることがあります。
特に猫背や首の前傾は、下あごが後方に押されるため口が開きやすくなり、口呼吸の習慣がつきやすくなります。毎日の積み重ねが歯並びを大きく左右するため、正しい姿勢を意識することが大切です。
食事中の姿勢と噛む力の関係

食事中の姿勢も歯並びに影響を与えます。お子さんが食事をしているとき、次のような姿勢になっていないか確認してみましょう。
–前のめりになっている
背中が丸くなり、噛む際の力が分散されやすくなります。
-足がブラブラしている
体が不安定になり、しっかり噛むことが難しくなります。
-テーブルの高さが合っていない
体勢が崩れやすく、食べにくくなります。
調査によると、ダイニングテーブルで食事をする子どもの約55%が「足が安定していない」と答えており、足が浮いていると噛む力が約15%低下することが分かっています。
そこで役に立つのが足置き台です。足をしっかり固定すると、噛む力が向上し、歯並びにも良い影響を与えます。食事中の姿勢を見直し、椅子の高さや足元の安定を調整することで、健康なあごの成長をサポートしましょう。
指しゃぶり・口呼吸が歯並びに与える影響

指しゃぶりや口呼吸の習慣は、歯並びに大きな影響を及ぼします。次のようなクセが続いていないかチェックしてみましょう。
–指しゃぶりを続けている
前歯が押し出され、出っ歯の原因になります。
–口を開けたままにしている
口周りの筋肉が弱まり、正しいあごの発達が妨げられます。
-同じ方向を向いて寝る
一方のあごばかり成長し、噛み合わせがズレることがあります。
指しゃぶりが長く続くと、前歯が前に押し出されたり、歯が並ぶスペースが不足してガタガタになることがあります。また、口呼吸が続くと舌の位置が下がり、歯並びが悪化しやすくなります。さらに、口内が乾燥し、むし歯や歯周病のリスクも高まるため、早めの改善が重要です。
歯並びを守るために今日からできること

歯並びの乱れを防ぐためには、生活習慣を見直すことが大切です。すぐにできる3つのポイントを紹介します。
1. 正しい姿勢を意識する
椅子には深く座り、背筋をしっかり伸ばすことを意識しましょう。また、机の高さは子どもの体に合ったものを選び、無理な姿勢にならないよう調整することが大切です。さらに、テレビやスマホを見るときも姿勢を崩さず、正しい姿勢を保つよう心がけましょう。
2. 足をしっかり固定する
足がしっかり安定するように、足置き台を活用すると良いでしょう。また、足が地面についているかを確認し、体がぐらつかないよう調整することも大切です。姿勢が安定し、あごの成長にも良い影響を与えます。
3. 指しゃぶり・口呼吸を改善する
成長期の子どもの体は柔らかく、日々の姿勢や生活習慣があごの発達や歯並びに影響を与えます。片側に体重をかける、猫背、ほおづえのクセは噛み合わせのズレにつながるため、早めの見直しが重要です。
また、食事中に足が浮いていると噛む力が弱まり、歯の発育に悪影響を及ぼします。さらに、指しゃぶりや口呼吸が続くと前歯が押し出され、正しい噛み合わせが保てなくなることもあります。
まとめ 毎日の習慣が未来の歯並びを決める!

成長期の子どもの体は柔らかく、日々の姿勢や生活習慣があごの発達や歯並びに影響を与えます。片側に体重をかける、猫背、ほおづえなどのクセは噛み合わせのズレにつながるため、早めに見直すことが大切です。
また、食事中に足が浮いていると噛む力が弱まり、歯の発育に悪影響を及ぼします。指しゃぶりや口呼吸が続くと前歯が押し出され、正しい噛み合わせが保てなくなることもあります。
毎日の小さな意識の積み重ねが、将来の歯並びや健康なあごの成長を左右します。今日からできることを実践し、子どもの健やかな成長をサポートしましょう!