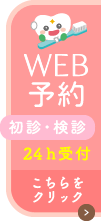Warning: Undefined variable $isThumbnail in /home/ikgreen7/yonago-harmy-dc.com/public_html/content/wp-content/themes/yonago_temp/content.php on line 27
米子ハーミー歯科では、白水貿易株式会社さんが販売している2つの器械を組み合わせることで世界レベルの感染対策を行います。今回はそのシステムについて説明します。 『ミーレ・ジェットウォッシャーPGシリー...続きを読む
Warning: Undefined variable $isThumbnail in /home/ikgreen7/yonago-harmy-dc.com/public_html/content/wp-content/themes/yonago_temp/content.php on line 27
メインテナンスとは、しっかりとセルフケアを行い、定期的に歯医者さんで歯のクリーニングを受けることです。歯を守るためには、ご自身での日々の歯磨き(セルフケア)とプロフェッショナルケア(プロケア)が両方...続きを読む
Warning: Undefined variable $isThumbnail in /home/ikgreen7/yonago-harmy-dc.com/public_html/content/wp-content/themes/yonago_temp/content.php on line 27
今回はメインテナンス(プロフェッショナルケア:以下プロケアと略)について具体的に説明します。 ①メインテナンスとは? 治療してキレイになったお口の中を“長時間維持する“には、治療後のメインテナンスが...続きを読む
Warning: Undefined variable $isThumbnail in /home/ikgreen7/yonago-harmy-dc.com/public_html/content/wp-content/themes/yonago_temp/content.php on line 27
歯周病の初期症状は痛くも痒くもならないために気づかない人も多く そのために歯周病は“沈黙の病気“と呼ばれているのです。 そのため、今回は歯周病の原因の復習とサインSOSについてお話します。 まずは、...続きを読む