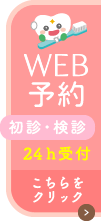「朝起きると顎がだるい」「歯がすり減ってきた気がする」「頭痛や肩こりが続いている」そんな不調に心当たりはありませんか?
その背景には、無意識のうちに行っている歯ぎしりや食いしばりが隠れているかもしれません。これらは歯や顎だけでなく、全身にまで悪影響を及ぼす怖い習慣です。今回はその種類や症状、さらにTCHについても解説します。
歯ぎしり・食いしばりとは?

歯ぎしりや食いしばりとは、上下の歯を強くこすり合わせたり、噛みしめたりする習慣のことです。特に就寝中に起こりやすく、本人が気づくのは難しいもの。
家族から「ギリギリ音がしている」と指摘されて初めて知るケースも少なくありません。主なタイプは3つに分けられます。
①グラインディング(歯をこすり合わせるタイプ)
もっとも一般的なタイプで、上下の歯を横にギリギリとこすり合わせます。睡眠中に大きな音が出るのが特徴で、家族に気づかれることが多いです。摩擦によって歯がすり減り、知覚過敏や亀裂を引き起こすリスクがあります。
②クレンチング(強く噛みしめるタイプ)
音が出ないため気づきにくく、無意識に強く噛みしめてしまうタイプです。ストレスや緊張時、日中の集中作業でも現れることがあります。歯や顎への負担が大きく、肩こりや頭痛など全身の不調につながります。
③タッピング(カチカチ噛み合わせるタイプ)
上下の歯を小刻みにカチカチと合わせるタイプです。頻度は少ないものの、長期的に続くと顎関節や歯の摩耗を招くことがあります。小さな習慣に見えても、軽視できません。
歯ぎしり・食いしばりがもたらす症状

この習慣が続くと、歯や顎だけでなく体全体に影響が出ます。代表的な症状には以下が挙げられます。
- 歯のすり減り、ひび割れ、欠け
- 詰め物や被せ物が外れやすくなる
- 健康な歯でも揺れたり沈んだりする
- 知覚過敏の悪化
- 顎関節症による痛みや開閉時の音
- 顔や首の筋肉の疲労、慢性的な頭痛や肩こり
放置すると歯周病や噛み合わせの乱れにつながり、治療が難しくなるケースもあります。
食いしばりの力はどれくらい?
普段の食事でフランスパンを噛み切るときには約30キロ、おせんべいを割るときには約50キロの力がかかります。しかし歯ぎしりや食いしばりでは80キロ近くに達することもあります。これは自分の体重に相当する圧力を歯にかけている状態です。その力が睡眠中に長時間かかれば、歯や顎に大きなダメージを与えるのは当然です。
TCH(歯列接触癖)とは?
歯ぎしりや食いしばりと並んで注目されているのがTCH(歯列接触癖)です。強く噛むわけではなく、日常生活の中で上下の歯を軽く触れさせ続ける癖を指します。
本来は安静時に2〜3ミリの隙間があるのが正常ですが、集中しているときやスマホ操作中などに無意識で歯が接触してしまいます。長時間続くと顎の疲労や口の開けにくさ、知覚過敏や歯周病の悪化につながることがあります。小さな習慣に思えても油断は禁物です。
自覚しにくいのが問題
歯ぎしりや食いしばり、TCHは無意識で行うため自分では気づきにくいのが特徴です。次のようなサインがあれば注意が必要です。
- 朝起きたときに顎がこわばる
- 歯の噛み合わせ面が平らにすり減っている
- 舌の横にギザギザの跡がある
- 頬の内側に白い線や噛み跡がある
- 慢性的な肩こりや首のこり
思い当たるものがある方は、早めに対策を始めましょう。
改善のためにできること

歯科医院では就寝時に装着するマウスピース(ナイトガード)が一般的です。透明な樹脂で作られ、歯にかかる力を分散し、すり減りや破折を防ぎます。保険適用できる場合もあり、毎晩続けることで効果が期待できます。
さらに、日常生活では「上下の歯を離す」意識を持つことが大切です。机やスマホに「歯を離す」と書いたメモを貼る、気づいたときに深呼吸をして力を抜く、ストレスを減らす工夫をするといった習慣が改善につながります。
まとめ

歯ぎしりや食いしばり、TCHは誰にでも起こり得る身近な習慣ですが、自覚しにくいため放置されやすいのが厄介です。気づいたときにはすでに歯の摩耗や顎関節症、全身の不調につながっていることもあります。
大切なのは「上下の歯をくっつけない」というシンプルな意識。歯科医院でのチェックと日常の工夫を組み合わせることで、歯と体を長く守ることができます。今日から少しずつ意識してみましょう。