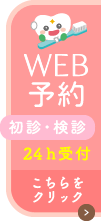「毎日歯磨きしているのに虫歯ができる…」「歯医者で“磨き残しがあります”と言われた」
そんな経験はありませんか?
実は、歯ブラシだけでは歯の表面の汚れの約60%しか落とせないと言われています。特に歯と歯の間や奥歯の裏側などは毛先が届きにくく、磨き残しがたまりやすい場所です。この磨き残しが虫歯や歯周病の原因になります。
そこで今回は、歯科医も推奨するデンタルフロス・歯間ブラシ・タフトブラシという3つの補助清掃用具の使い方と注意点を解説します。正しく使えば、虫歯や歯周病の予防効果が格段に高まります。
なぜ補助清掃用具が必要なのか?
毎日の歯磨きだけでは、どうしても落としきれない汚れが残ってしまいます。こうした歯垢は、わずか1〜2日で硬い歯石に変化し、一度歯石になると自宅でのケアでは除去できず、歯科医院での専門的な処置が必要になります。
特に歯と歯の間や奥歯の裏側、歯並びが重なっている部分は汚れがたまりやすく、通常の歯ブラシでは届きにくい場所です。そのため、デンタルフロスや歯間ブラシといった補助清掃用具を活用し、日常的に汚れを取り除く習慣が欠かせません。
補助清掃用具の正しい使い方まとめ

歯ブラシだけでは落としきれない汚れを取り除くためには、デンタルフロス、歯間ブラシ、タフトブラシの3つを使い分けることが大切です。ここでは、それぞれの特徴と具体的な手順をご紹介します。
デンタルフロス
デンタルフロスは、歯と歯の間や歯ぐきのきわの歯垢を除去する糸状の清掃用具です。歯ブラシでは届かない部分の磨き残し対策に効果的で、指巻きタイプとホルダータイプの2種類があります。
①指巻きタイプ
- フロスを30〜40cmにカットする。
- 両手の中指に2〜3回巻きつける。
- 親指と人差し指で1〜2cmの間隔を保つ。
- 歯と歯の間にゆっくり差し込む。
- 歯の側面に沿わせて上下に動かし、汚れをかき出す。
②ホルダータイプ
- 持ち手部分をしっかり持つ。
- 歯と歯の間にゆっくり差し込む。
- 歯の側面に沿わせて上下に動かす。
・ポイント
無理に押し込まず、歯ぐきを傷つけないように優しく使いましょう。使用は1日1回、就寝前が理想です。
歯間ブラシ
歯間ブラシは、歯と歯の間にすき間がある方や、歯ぐきが下がって歯根が露出している方に特に向いています。小さなブラシがすき間にフィットし、食べかすや歯垢を効率的にかき出すことができます。ブリッジやインプラントまわりなど、フロスでは届きにくい場所の清掃にも役立ちます。
手順
- 鏡で歯と歯の間の状態を確認する。
- 歯ぐきを傷つけないよう、ブラシを水平にゆっくり差し込む。
- 前後に2〜5回動かして汚れを取り除く。
- 使用後は流水でブラシを洗う。
- 風通しの良い場所で乾燥させる。
・ポイント
自分の歯間に合ったサイズ(SSS〜LL)を選び、無理に通さないようにしましょう。1日1回、就寝前の使用がおすすめです。
タフトブラシ(ワンタフトブラシ)
タフトブラシは、毛先が小さくまとまっており、通常の歯ブラシでは届きにくい部位の清掃に最適です。奥歯の裏側、歯並びの重なった部分、矯正装置の周囲、ブリッジやインプラントのまわりなど、ピンポイントで磨きたい場所に向いています。
手順
- 奥歯の裏や歯並びの重なり、矯正装置やブリッジまわりなど、磨きたい部位に毛先を向ける。
- 毛先を歯の面に対して約45度の角度で当てる。
- 小刻みに左右へ動かし、1本ずつ丁寧に磨く。
- 使用後は流水で洗い、しっかり乾燥させる。
・ポイント
力を入れすぎず、なぞるように優しく当てることで歯や歯ぐきを傷つけずに清掃できます。
よくあるトラブルと解決法

フロスが歯間に入りにくい、または糸が切れてしまう場合は、滑りの良いワックス付きフロスがおすすめです。それでも引っかかる場合は、虫歯や詰め物の段差が原因かもしれないので歯科医院で相談しましょう。
使用時に出血する場合は、歯ぐきに炎症がある可能性があります。毎回出血するなら無理をせず歯科で診てもらいましょう。初めだけの軽い出血であれば、正しい使い方を続けることで改善することが多いです。
まとめ:毎日のひと手間が未来の歯を守る

デンタルフロス、歯間ブラシ、タフトブラシを歯磨きにプラスするだけで、磨き残しを減らし、虫歯や歯周病のリスクを大きく下げられます。最初は面倒に感じても、毎日1〜2分の習慣が将来の歯の健康を守ります。
「全部は無理」という場合も、自分に合ったケアから始めてみましょう。