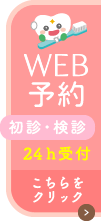「前歯がうまく噛み合っていない気がする」「いつも口がぽかんと開いている」
そんな様子に心当たりはありませんか?
子どもの歯並びの乱れは、見た目だけの問題ではありません。発音や噛む力、呼吸の仕方、さらには全身の健康やあごの発達にも深く関わってきます。
しかし、歯並びのトラブルは、早めに気づいて対応すれば改善の可能性が高いです。この記事では不正咬合のタイプから予防する対策まで、詳しく解説します。
よくある不正咬合のタイプ
不正咬合(ふせいこうごう)とは、噛み合わせに問題がある状態のことをいいます。代表的な6つのタイプをご紹介します。
①開咬(かいこう)
開咬とは、奥歯は噛んでいるのに前歯が閉じていない状態です。前歯に隙間ができるため、口が開きやすくなり、口呼吸の習慣がつきやすくなります。この癖が続くと虫歯や歯周病のリスクも高まります。
②上顎前突(じょうがくぜんとつ)
いわゆる「出っ歯」の状態です。前歯が突き出ていることで転倒時に前歯をぶつけやすくなります。また見た目を気にする子どもも少なくありません。
③反対咬合(はんたいこうごう)
下の前歯が上の前歯よりも前に出ている噛み合わせです。発音がしづらくなったり、食べ物をしっかり噛めないことがあり、消化への影響も懸念されます。
④交叉咬合(こうさこうごう)
上下の奥歯の噛み合わせが左右にずれている状態です。顔のバランスに影響が出たり、片側だけで噛むクセがつくこともあり、あごの成長に偏りが出やすくなります。
⑤過蓋咬合(かがいこうごう)
上の前歯が下の歯を深く覆ってしまっている噛み合わせです。あごの関節に負担がかかりやすく、食事や発音のしづらさ、関節の痛みなどの原因になります。
⑥叢生(そうせい)
歯がきれいに並ばず、重なり合ってガタガタに生えている状態です。歯ブラシが届きにくいため、虫歯や歯周病のリスクが高まり、咬合機能や見た目にも影響を及ぼします。
なぜ歯並びが悪くなるの?

歯並びの乱れは、遺伝だけでなく日々のクセや生活習慣が影響していることも多いです。
- 指しゃぶりやおしゃぶりの長期使用
- 飲み込むときに舌が前に出る「舌癖」
- 慢性的な口呼吸
- 猫背や前かがみの姿勢
- 片側だけで噛むクセ
- 柔らかい食事ばかりで噛む力が育たない
こうした行動が、歯並びやあごの発達に影響します。
家庭で気づけるサインとは?
子ども自身が「噛みにくい」「歯が変」と気づくことは少ないです。実際に、気になる様子があっても言葉にできないことが多いです。だからこそ、保護者の観察がとても大切になります。
お子さんに、次のような様子は見られませんか?
- いつも口が開いている
- 食べ物を前歯で噛み切れていない
- 発音が聞き取りにくい(特にサ行・タ行)
- 舌を前に出すクセがある
- 指しゃぶりや布を噛むクセが長引いている
- 食べるときに左右どちらかに偏っている
これらは不正咬合のサインかもしれません。早めに歯科医院で相談してみましょう。
今日からできる!歯並びを守る6つのポイント

不正咬合の予防や改善には、日々の生活習慣がとても重要です。ここでは、家庭で今日から実践できる6つの対策をご紹介します。
①クセをやめる工夫をしよう
指しゃぶりや爪かみ、寝るときに布を噛むクセなどは、不正咬合の大きな原因になります。特に指しゃぶりは4歳ごろまでに卒業させるのが理想的です。無理にやめさせるのではなく、スキンシップを増やしたり、手を使う遊びを取り入れることで、自然にやめられるようサポートしていきましょう。
②舌・唇・飲み込みのトレーニング(MFT)
MFT(口腔筋機能療法)は、舌や口まわりの筋肉を鍛えるトレーニングです。たとえば、舌を上あごにつける、口を閉じる習慣をつける、飲み込むときに舌を出さないようにするなどが効果的です。歯科医院で指導を受けることもできますが、内容によっては自宅でも簡単に取り組める練習が多いため、日常生活に取り入れやすい点もメリットです。
③鼻呼吸の習慣をつける
口呼吸は歯並びやあごの成長に悪影響を及ぼします。日頃から鼻で呼吸する習慣を意識づけましょう。食事前には鼻をかむ、眠る前に口を閉じているか確認するなど、小さなことから始めてみてください。鼻づまりがある場合は耳鼻科の受診も検討しましょう。
④姿勢を整える
猫背や前かがみの姿勢は、あごの位置や噛み合わせに悪影響を及ぼすことがあります。食事や勉強のときには、椅子と机の高さを調整し、足がしっかり床につくようにしましょう。また、鉄棒やぶら下がりなどの運動を取り入れて体幹を鍛えることも、姿勢の改善とあごの発育をサポートします。
⑤よく噛んで食べる習慣を
噛む回数が少ないと、あごの発育が不十分になり、歯が並ぶスペースが足りなくなることがあります。玄米や根菜など噛みごたえのある食材を取り入れたり、テレビや音楽を消して集中できる環境で食事をすることも大切です。
⑥バランスよく噛む
片側だけで噛むクセがあると、あごの成長に偏りが出てしまいます。食事の際は、左右両方を使って噛むことを意識しましょう。ガムやせんべいなど硬めの食べ物を使って、左右交互に噛むトレーニングを行うのもおすすめです。
まとめ:歯並びの乱れは早めの気づきと対策がカギ!

不正咬合は、放っておくと将来的に健康面や心理面でも影響が出ることがあります。しかし、早期に気づいて正しい対策をとれば、十分に改善が期待できるものです。
「なんとなく気になるな」と感じたら、ぜひ当院までご相談ください。日々の習慣を見直しながら、お子さんの健康な歯並びを一緒に守っていきましょう!