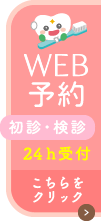「最近、食事中によくむせるようになった」「飲み込みにくい感じがする」「食べるとやたら疲れる」そんな変化に心当たりはありませんか?
これらはもしかすると、摂食嚥下障害のサインかもしれません。
食べるときの「噛む・飲み込む」といった動作は、ふだん無意識に行っているものです。しかし、加齢や病気、筋力の低下によって、こうした動作がうまくできなくなることがあります。その結果、誤嚥性肺炎といった命に関わる病気を引き起こすこともあるため、早めの対策が大切です。今回は嚥下に関する障害や予防方法などを詳しく解説します。
摂食嚥下障害ってどんなもの?
摂食嚥下障害とは、「食べる」ための動きがスムーズにできなくなる障害です。代表的な症状には、次のようなものがあります。
- 飲み物を飲むときにむせやすい
- 食べ物が喉につかえる感じがある
- 食後に声がかすれる・ガラガラする
- 食事に時間がかかる、残すことが増えた
これらを「年齢のせい」と見過ごす方も多いです。しかし、放置すると脱水や栄養不足、そして誤嚥性肺炎のリスクが高まります。とくに高齢者の場合、誤嚥性肺炎は死亡原因の上位にある深刻な病気です。
原因はひとつじゃない
摂食嚥下障害の原因は、主に以下の3つに分けられます。
① 器質的な原因
口内炎や歯周病、舌の腫れ、喉の腫瘍など、構造的な問題によって飲み込みづらくなるケース。
② 機能的な原因
加齢や脳卒中、パーキンソン病などにより、嚥下に関わる筋肉や神経の働きが低下するケース。
③ 心理的な原因
うつ病や不安障害、ストレスなどによって、食欲不振や喉の違和感が起こるケース。
原因によって対処法も変わるため、自己判断は禁物です。早めに専門医に相談しましょう。
誤嚥性肺炎ってなに?

誤嚥性肺炎とは、食べ物や飲み物、唾液、さらには口の中に存在する細菌が誤って気管に入り、肺に炎症を引き起こす病気です。通常、私たちが飲み込むときには、気管の入口が自動的に閉じるしくみがあり、異物が肺に入らないように守られています。しかし、嚥下機能が低下するとこの働きがうまくいかず、誤嚥が起こりやすくなります。
特に注意したいのが「不顕性誤嚥」です。これは、むせたり咳き込んだりせず、本人も気づかないうちに誤嚥が起こる状態を指します。知らないうちに肺炎が進行し、体力を奪ってしまう危険があります。
高齢者や嚥下機能が低下している方はリスクが高いため、予防と早期発見がとても重要です。
誤嚥性肺炎を防ぐ3つのポイント

誤嚥性肺炎は予防が可能な病気です。以下の3つを意識するだけで、リスクを大きく下げることができます。
1. 口腔内を清潔に保つ
歯みがきやうがい、舌の掃除を毎日欠かさずに行いましょう。特に高齢者の場合、自分で磨ききれないこともあるため、定期的に歯科でのケアを受けるのもおすすめです。
2. 免疫力を保つ
バランスの良い食事、十分な睡眠、軽い運動で体力を維持しましょう。小さな生活習慣の積み重ねが、感染を防ぐ強い体をつくります。
3. 飲み込む力を鍛える
嚥下体操や口の体操を日常的に行うことで、舌や口まわりの筋力低下を防ぐことができます。トロミをつけたり、柔らかい食事にするなど、調理法にも工夫をしましょう。
不安を感じたら専門家へ
症状がなかなか治まらなかったり自分なりに工夫しても改善しなかったりする場合は、我慢せずに専門家へ相談しましょう。摂食嚥下障害は、歯科医師や耳鼻咽喉科医、言語聴覚士など、複数の専門職が連携して対応するチーム医療が基本です。原因や症状に応じた適切な診断とリハビリが受けられることで、改善の可能性がぐんと高まります。
自己判断で放置することは、症状の悪化や全身の健康への影響にもつながりかねません。早めに受診することで、体への負担を減らし、安心して食事を楽しめる毎日へとつながっていきます。
まとめ

「むせる」「飲み込みづらい」「食事がつらい」そんな違和感があるときは、摂食嚥下障害のサインかもしれません。放っておくと命に関わる誤嚥性肺炎につながることもあるため、早めの気づきと対策がカギになります。
日々の口腔ケアと体力維持、そして機能回復トレーニングを意識して、これからも安心して食事を楽しめるようにしましょう。