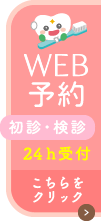「歯磨きのときに血が出る」「口臭が気になる」「歯がグラグラしてきた気がする」
そんな症状を感じたことはありませんか?それは、歯周病のサインかもしれません。
初期のうちは痛みも少なく、「そのうち治るだろう」と放置してしまう方も多いのですが、気づかないうちに少しずつ進行していくのが歯周病の怖いところです。
この記事では、歯周病の原因や進み方、体への影響、そして今日からできる予防とケアの方法をお伝えします。
歯周病の原因と進行
歯周病は、歯と歯ぐきのすき間にたまったプラーク(歯垢)に潜む細菌が引き起こします。この細菌が炎症を起こすことで、歯ぐきが赤く腫れたり、出血が起こったりします。
初期の「歯肉炎」であれば、適切なケアで健康な状態に戻すことが可能です。しかし、進行して「歯周炎」になると、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けはじめ、歯がぐらついてしまいます。最終的には歯を失うリスクも高まります。
歯周病が怖いのは、痛みや腫れなどの自覚症状が少ないまま進行する点です。だからこそ、早めのチェックと予防ケアが大切なのです。
口だけの問題ではない、全身への影響

歯周病は口の中だけにとどまりません。最近の研究では、全身の病気との関係も明らかになっています。
まず、糖尿病との関わりです。歯周病は進行すると炎症物質が血糖値のコントロールを悪化させます。逆に、糖尿病があると免疫力が落ち、歯周病が悪化しやすくなります。お互いが悪循環を起こす関係にあるのです。
また、心臓病や動脈硬化にも影響します。歯周病菌が血液中に入ることで血管を傷つけ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めることが報告されています。
さらに、骨粗鬆症や妊娠中のトラブルにも関係します。女性は閉経後に骨密度が低下しやすく、歯を支える骨ももろくなりやすいです。妊婦さんでは、歯周病による炎症物質が子宮に作用して早産や低体重児出産のリスクを上げることがあるのです。
高齢期の健康寿命にも影響
歯を失うと、噛む力が落ちて食事の幅が狭くなります。その結果、タンパク質やビタミンなどが不足し、筋力や免疫力の低下に繋がります。筋力や免疫力が衰えると「フレイル」と呼ばれる虚弱状態に陥りやすくなるのです。
また、噛む刺激が減ることで脳の働きにも影響が出るとされ、認知症の発症や進行と関係していることもわかってきました。歯を守ることは、人生の質を守ることでもあるのです。
歯周病と感染リスク

歯周病が進むと免疫力が下がり、風邪やインフルエンザなどの感染症にもかかりやすくなります。歯ぐきのポケットに細菌がたまると、そこからウイルスが体内に入り込みやすくなるためです。定期的に歯科でクリーニングを受けている人は、感染症の発症率が低いという報告もあります。
口の中を清潔に保つことは、体全体の防御力を高めることにつながります。
歯周病の予防とケア
歯周病は自然に治ることはありませんが、早期発見と予防で進行を止めることができます。
まずは、正しいブラッシングを習慣にしましょう。歯と歯ぐきの境目を意識して、やさしく小刻みに動かします。歯ブラシだけでは落としきれない汚れには、デンタルフロスや歯間ブラシを使うのが効果的です。
そして、定期的な歯科メンテナンスも欠かせません。歯石は自分では取れないため、3〜4か月ごとのスケーリングやクリーニングでプロに任せましょう。
また、バランスのとれた食事、十分な睡眠、禁煙も大切です。生活習慣を整えることが、口の健康を支える土台になります。
まとめ

歯周病は「歯を失う病気」だけではなく、「体全体の健康」に関わる病気です。毎日のケアと定期検診を続けることで、歯も体も長く守ることができます。
小さな出血や違和感を見逃さず、今日からできるケアを始めてみましょう。
それが、あなたの歯と健康寿命を守る第一歩です。