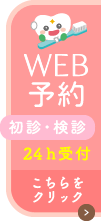「最近、口の中がネバネバする」「話しづらい」「食べ物の味がしない」こんな症状に心当たりはありませんか?
実はこれ、唾液の減少や口呼吸のクセが原因かもしれません。唾液は、口だけでなく全身の健康にも深く関わる大切な存在です。ここでは、唾液の働きと減少による影響、改善のための習慣やケア方法をご紹介します。
唾液の6つの役割
健康な人の体では、1日に約1〜1.5リットルの唾液が分泌されています。単なる水分ではなく、さまざまな重要な働きがあります。
1. 虫歯を修復・予防する
酸を中和し、カルシウムやリンを補給して再石灰化を促します。初期段階の虫歯なら、唾液の力で自然修復されることもあります。
2. 口内環境を整える
緩衝作用で酸性に傾いた口内を中性に戻し、免疫物質や抗菌成分で菌の繁殖を抑えます。
3. 飲み込みやすくし粘膜を守る
食べ物をスムーズに飲み込みやすくし、唇や舌、頬の粘膜を保護します。口内炎や傷の予防にもつながります。
4. 消化を助ける
唾液に含まれる消化酵素アミラーゼがでんぷんを分解し、胃腸への負担を減らします。
5. 味覚をサポートする
食べ物の味の成分を舌の味蕾へ届け、食事をおいしく感じやすくします。
6. 口臭を防ぐ
自浄作用で食べかすや細菌を洗い流し、口臭の発生を防ぎます。
唾液量を増やすための5つの習慣

唾液は、日常生活のちょっとした工夫で分泌を促すことができます。
1. よく噛む
1口につき30回を目安に噛むことで唾液腺が刺激されます。繊維質の多い食材を選ぶのも効果的です。
2. おしゃべり・舌トレーニング
会話や歌で声を出したり、舌を上下・左右・回す体操で筋肉を鍛えると、唾液が出やすくなります。
3. 唾液腺マッサージ
耳下腺・顎下腺・舌下腺をやさしく円を描くようにマッサージします。リラックスしながら行うのがコツです。
4. 水分補給をこまめに
喉が渇く前に少しずつ飲む習慣をつけ、脱水による唾液減少を防ぎましょう。
5. 歯科医院で相談する
口の渇きや口臭が気になる場合は唾液検査で原因を特定し、適切なケアを受けましょう。
口呼吸の悪影響と対策

口呼吸が習慣化すると、健康面だけでなく見た目にも大きな影響を及ぼします。例えば、風邪や感染症にかかりやすくなったり、唾液の減少によって口臭や虫歯の原因菌が増えたりします。
また、舌や筋肉のバランスが崩れて歯並びが悪くなるほか、成長期の子どもではあごが後退し、顔立ちが変化してしまうこともあります。こうした影響を防ぐためには、まず原因を知ることが大切です。
原因別の対策
口呼吸の改善には、原因に応じたアプローチが必要です。原因ごとに適した方法を選ぶことで、より効果的に鼻呼吸へと切り替えることができます。ここでは、代表的な3つの原因とその対策を紹介します。
1. 鼻づまりが原因
慢性的な鼻炎やアレルギー性鼻炎の場合は耳鼻科での治療が必要です。小児矯正が有効なケースもあります。
2. 口の閉じにくさが原因
筋力不足や歯並びの問題が原因であれば、口周りの筋トレやマウスピース型装置の使用で改善します。
3. 習慣・クセが原因
正しい呼吸法や姿勢を専門家の指導で身につけることが効果的です。
家庭でできる口の乾き対策

ちょっとした生活習慣の見直しで、乾燥や口呼吸を防げます。
1. 鼻呼吸を意識する
普段の姿勢や表情に注意し、口を閉じる習慣をつけましょう。
2. 室内の乾燥を防ぐ
加湿器で湿度40〜60%を保ち、エアコン使用時も乾燥対策を忘れず行いましょう。
3. 口を潤す工夫
のど飴やガム、キシリトール入りタブレットなどを取り入れ、唾液分泌を促します。また、外出時もペットボトルや水筒を持ち歩き、少しずつ水分を補給します。
まとめ

唾液は、虫歯・歯周病予防から口臭対策、味覚・消化・免疫サポートまで担う「天然の万能薬」です。口の渇きや味覚の変化を感じたら、今回紹介した生活習慣やケアを取り入れ、必要に応じて歯科医院で相談しましょう。早めの対策が、口と全身の健康を守る第一歩です。