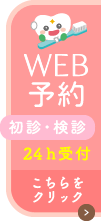「冷たいものがしみるけど、これって虫歯?」「昔治療した歯がなんとなく気になる…」そんな不安を感じたことはありませんか?実は虫歯は、初期段階では痛みなどの自覚症状がほとんどないまま進行することが多いです。なかには「気づいたら神経まで侵されていた」というケースも珍しくありません。
今回は虫歯の進行度と治療法、年齢によって変わるリスクや予防法についてわかりやすくご紹介します。
虫歯の進行は5段階に分かれる
虫歯は進行具合によって「CO」から「C4」までの5段階に分類されます。
① CO(要観察歯)
COは歯の表面が白く濁る初期の状態です。穴は開いていないため、削らずフッ素塗布やブラッシング改善で再石灰化が期待できます。
② C1(エナメル質の虫歯)
C1は歯の表面に小さな穴ができ始めますが、痛みはありません。虫歯部分を削り、プラスチックで補う軽度の治療で済みます。
③ C2(象牙質に達した虫歯)
C2は冷たいものがしみるようになり、虫歯が象牙質に到達する状態です。より深く削ってインレーやクラウンで修復する必要があります。
④ C3(神経に達した虫歯)
C3は激しい痛みが出る状態です。神経を取り除く根管治療が必要になり、治療回数も多くなります。
⑤ C4(歯根だけが残った状態)
C4は神経が死んで一時的に痛みがなくなる状態です。抜歯の選択肢も多く、ブリッジやインプラントなどの補綴治療が必要です。
虫歯ができやすい場所は?

虫歯は奥歯の溝や歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目などにできやすいです。これらの場所は歯ブラシが届きにくく、汚れがたまりやすいからです。特に高齢になると歯ぐきが下がって歯の根元が露出し、虫歯のリスクが高まります。
対策としては、フロスや歯間ブラシ、電動歯ブラシなどの併用が効果的です。部位に応じた適切なケアを心がけましょう。
虫歯の進行スピードは人それぞれ
虫歯の進行スピードには個人差があります。唾液の量や質、食生活、ブラッシングの習慣、さらには遺伝的な体質までもが関係しています。「まだ痛くないから大丈夫」と放置するのは危険です。
COの状態から何年も進行しない人もいれば、数ヶ月でC2に達してしまう人もいます。だからこそ、定期的に歯科検診を受け、虫歯の早期発見を心がけましょう。
高齢者に多い「根面う蝕」に注意
年齢を重ねると歯ぐきが下がり、歯の根元にある象牙質が露出して「根面う蝕」が起こりやすくなります。象牙質は酸に弱く、虫歯の進行が早いのが特徴です。
また、かぶせ物や入れ歯の境目、薬の副作用による唾液の減少、手先の不自由さによる清掃不良なども、虫歯リスクを高めます。複雑なかぶせ物の清掃には特に注意が必要です。
大人の虫歯は「再発」と「発見の遅れ」がポイント

大人の虫歯で多いのは、過去に治療した歯の再発や、神経を抜いた歯の虫歯です。被せ物と歯の間にできた隙間から細菌が入り込み、気づかないうちに虫歯が進行してしまうからです。
また、歯の間や根元など歯ブラシが届きにくい部分にできた虫歯は、痛みが出にくいため気づきにくく、発見が遅れる傾向にあります。
虫歯予防の基本は「毎日のケア」と「プロのチェック」
虫歯予防で大切なのは、日々のセルフケアと歯科での定期検診です。
- 正しいブラッシング
柔らかめの歯ブラシを使い、フッ素入りの歯磨き粉で歯と歯ぐきの境目を丁寧に行います。 - 歯間ケアの徹底
フロスや歯間ブラシで歯と歯の間の汚れを除去します。歯ブラシだけでは届かない部分を補います。 - 唾液ケアも大事
よく噛む食事や水分補給、キシリトール製品の活用で唾液の分泌を促します。 - 定期検診の習慣化
レントゲンによる早期発見や、クリーニングによる予防処置でリスクを抑えましょう。3〜4ヶ月に一度の受診が目安です。
まとめ

虫歯は初期段階であれば簡単な処置で済みます。しかし、放置すると神経治療や抜歯につながることもあります。年齢によってリスクや対策も異なりますが、毎日の丁寧なケアと歯科医院でのチェックを継続することで、虫歯予防は可能です。
あなたの大切な歯を守るために、今からできることを見直してみませんか?